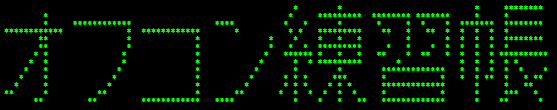NECのオフコン情報掲示板(いろいろ)
| NECのオフコンに関しての最新情報、面白い話、昔の思い出、何でも自由に書いてください。 |
| 新規投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ |
| Re: 将来600シリーズは巨大なドンガラ(空洞)と化すか? | |
| ターラヤン 2004-1-26 16:51:58
[返信] [編集] 極一部の人は、最近はホスト集中に戻ってきたとか言っていますが、 やはり分散形態が一般的だと思いますし、 A−VXの上で動くソフトとWindows上のソフトを複数のサーバに分けて、 運用した方がより安定するのは確かだと思います。 (A−VXをwindows上で動かしている限りは、Windows上の変なソフトの 影響をA-VX側が受けてしまう可能性は否定できませんし。) 一方、やはり世間の流れから見れば、徐々にA-VX上のソフトをWindows 上で動くようにしたいという話もあり、だんだんA-VX上で動くソフトを 減らしていく傾向にあるのではないかと思います。 (オフコンのサイトを立ち上げている私としては、残念な話ですが。) そして残ったソフトもWindows上のソフトと連携させて動かすもののみ となってしまうのかもしれません。 ただ、そういう使い方をするところは、空洞になった段階で全部Windowsに 行ってしまい、600シリーズは捨ててしまうのではないでしょうか。 逆に今まで通りA-VXを使用しつづけるところは、空洞になることもなく、 600シリーズを十分に使い尽くす可能性もあります。 結局空洞にするかどうかは使い方次第だと思います。 | |
| 「将来600シリーズは。。」 の(注釈)です | |
| EXCHANGE 2004-1-25 22:08:19
[返信] [編集] > 「RDBQ」や「skylink」で大規模な検索をかけると「業務側」がグッと遅くなったり止まったりした記憶がおありではないだろうか? * A−VXをよくご存じない方が誤解してはいけないので、上記の部分に注釈を付け加えておく。 * 正確には「グッと遅くなったり、しばし止まったようになったり」というのが正しい。 我がA−VXにおいてはWindowsのように負荷がかかってハングアップしてしまうなどということは、まずありえないことである。 * 筆者が恐れるのはWindows上で、A−VXの業務とWindows上の負荷のかかる業務とを同時に稼働させた場合、Windowsの道連れになってA−VX業務までコケてしまうことである。 | |
| 将来600シリーズは巨大なドンガラ(空洞)と化すか? | |
| EXCHANGE 2004-1-25 20:42:18
[返信] [編集] * 日本Unisysという会社のHPを訪れて、この会社の汎用機「CS7801−185」や「CS7402」「CS7201」などの資料をごらんいただきたい。 ここではCMPというテクノロジーが使われ従来型ホスト系OSと新しいオープン系OS(といってもWindowsのことだが)を同じ筐体内で同時に稼働させるようになっている。 CS7201に至ってはすべてのCPUがインテル製で、ホストOSの方はインテルCPU上にエミュレーションソフトをかませてその上で稼働し、また同時にWindowsも稼働するようになっている。これは一見我らが600シリーズと非常によく似たやり方にみえる。 * ところでUnisysのようなやり方は現代のホスト系マシンではそれほど特異な方法ではない。それどころか「ホストOS」を中心に据えながら同一筐体内で「windows」さらには「Linux」など複数のオープン系OSを稼働させ連携を計るという方法はホストの世界では今日主流となっているといえる。 * こういう観点から見れば、NECが700シリーズから始めて600シリーズに至る一連の製品でWindows上でAーVXを稼働させてきた方法論は時代の本流に沿ったやり方であるといって間違いないだろう。(ハードだけをPC系に換えOSはホスト系ASPのみの改良で押し通す富士通はまさにオフコン原理主義といえるかもしれない) * さて、600シリーズに携わっておられる技術者、担当者の方は最近になって何か「あること」に気づいておられるのではないだろうか? ハードウェア、とりわけメモリ、ディスクなどの低価格化で600シリーズにおいても新モデル(直近では600xi)が発売されるたびにスペックは拡大し続け、今や下位モデルにおいても少し増設すればメモリ1G以上、ディスク100Gなどというのが十分可能になった。 * 問題は、さてそこで、だ。 旧S7200(オフコン)のわずかディスク900MB×2台程度で「基幹業務」をこなしていたシステムの「資産継承」を「スムーズ」に行ったところで「はた」と困ってしまうのだ。 余ったディスク領域を一体何に使えば良いのか? 現時点においてはこうした考えは「一瞬、担当者の頭をよぎる程度のもの」かもしれない。 MSDを(使わないと分かっていても)大きめに取ったり、NT連携領域と称するものを「将来きっと使うだろう」などといって大きめに取ったり。。作業する者はある程度自分を納得させることはできるだろう。 しかし「今後さらに新製品が出てどんどん容量が大きくなったとき一体どうすれば良いのか?」 * こういった問題を経営者が聞きつければ「それでは1ランク下のモデルを買えば!」と叫ぶだろうが、主催者側(供給側?業界側?)はそうもいかないだろう。オープン化の流れを吸収し、顧客の求める新しい領域(「貴重なデータの活用」「複数サーバTCOの削減」等)を切り開き、業界を繁栄させるためには、Unisys社が行っているような「1台で??台の効果」がぜひとも必要なのである。 * こういうと、読者は「600シリーズはすでに前述の通りA−VXとindowsが同時に稼働して利用できるシステムとして設計されているのではないか?」と思われるかもしれない。 それは正しいが、ある意味で間違っている。 実は600シリーズのやり方とUnisysのやり方には大きな違いがある。 * Unisysの方式では、複数のCPU、巨大なメモリを持っていても、それらは「論理的な区画」によって分割されておりそれぞれの「区画」に別々の資源(CPU等)を割り当てることが出来る。 つまり「区画間の負荷」を調整、制御出来るのである。 * 翻って我が「600シリーズ」を考えてみよう。 まず、純オフコン(S3100、S7200等)だった頃を思い出して欲しい。「RDBQ」や「skylink」で大規模な検索をかけると「業務側」がグッと遅くなったり止まったりした記憶がおありではないだろうか?(業務ソフトウェア側で大量の検索を行なって言う場合も同様である)この種のDB検索はA−VXの場合ほとんどが全件検索になってしまい、CPUに大きな負荷がかかってしまう。 この傾向は600になっても同様である。(もちろんCPU性能が劇的に向上している分だけ改善しているのは事実ではあるが。) そして、RDBQ2等で大量の検索をかけているときWindowsのタスクマネージャで観察すれば分かるが、CPU使用率がグッと高くなるが、メモリ使用量はほとんど増えていない。 * A−VX側ソフトウェアからDB検索させる場面で、oracleやSQLサーバなどを同時に稼働させて「情報系」を構築したり、TS機能を使ってofficeなどを集中管理しようとしても、同じWindowsw上で稼働しているためお互いの負荷を制御しにくくなってしまい、運用上非常に問題があるといえる。 「windows上でA−VXが稼働する」といいつつ、NECのカタログなどを見ていると拡張された部分はほとんど「別サーバ」になっているのはそのためではないだろうか? そして、ほとんどのwindows業務を別サーバにしてしまった状況で残っている連携機能は富士通の純粋オフコンOSでも可能な程度の変更機能なのである。 (ということは、windowsはintelチップとA−VXの間の単なる「巨大なファームウェア」にすぎなくなってしまい、windowsと共存させた意味はあまりなくなってしまうのである。) * 負荷のかかる業務は結局A−VXのみしか出来ないとすれば、前述のRDBQの動作をみても分かるようにメモリをある程度を超えて増やしてもあまり意味はなく、基幹業務のみでは増大し続けるディスクをいつかもてあまして、有効利用できなくなってしまうのではないだろうか? * かくて、将来の600シリーズにおいては、 有り余るハードウェア資源を前にして、 顧客に 「手のひらサイズに近づいていく下位機種を勧めるか」 「必要だと偽って、巨大なドンガラ(空洞)を販売するか」 のいずれかの道を歩むことになってしまうのではないだろうか? * 以上は、筆者の独断と偏見に満ちた見解であり、最新の600シリーズ上で負荷のベンチマークを行ったわけではないので、不正確である可能性は高い。 しかし、筆者の心配事が杞憂であることを祈る。 | |
| (続報)謎の620xi−Sについて | |
| EXCHANGE 2003-12-31 12:39:11
[返信] [編集] * その後いろいろ調べてみましたが、 (1)OSは、Windows−serverではなく、XPまたは2000のプロフェッショナルを使用。もちろんA−VX01がインストールされているので、A−VXのサーバとして使う分には特に問題なし。 (2)基本構成では、バックアップ装置、UPS、アレイは付いていない(オプションで可。ただしアレイはミラー)。 (3)WS台数は3台まで?タスク数5まで?(いずれも未確認情報) (4)利用できない主なユーティリティソフトまたは機能 * OSV−GUI実行 * FAX連携 * OpenDatabaseAccessKit * BizReporting * ジョブ起動ユーティリティ * PrintView という感じです。 いずれもNECに確認したわけではありませんので、担当セールスにご確認頂きたいのですが、 もし上記の通りだとすれば、やはりターラヤンさんのご指摘通り、 従来機能中心で比較的小規模な方向きでしょうか。 積極的に新機能を使いたい方や、今後端末を拡張する可能性のある方は620xi以上を選択すべきでしょう。 (中小の会社の場合620xiは賢い選択かもしれません) | |
| Re:620xi−sの件(補足) | |
| 江須扇 2003-12-26 3:45:47
[返信] [編集] 620xi−sは最低限の構成になっているので、 ターラヤンさんの説明の通り UPSが無い backup装置が無い(FDUだけ) という事で、例えばネットワークでカバーするという事考えた場合、 A−VX/NETを入れるだけでも有償ソフトなのでそれなりに費用がかかります。 また、開発マシンとしてCOBOL85とSMART2(EUF機能の代替も兼ねて)と合わせて3有償ソフトを入れるとハードと同じ位の費用が掛かりそうです。 ところで、今回のxiシリーズは640Ai−Rに相当するものはなくなったのでしょうか? 高さが1Uでしたが今回の640xiのラックモデルは5Uです。 ラックに複数台いれるとすぐいっぱになりそうです。 そこで、ちょっと早とちりですがひょっとして次のOSでは、 一台の中で複数のA−VXを立ち上げることできエミュレータはport番号で切り替えてできるというようなことを考えているのではと思っております。 A−VX/NETでやり取りできるが主OS以外はPC/WS−EMLだけで周辺装置は使えないという制約はあると思いますが・・・ | |
| 620Ai-S/620xi-Sについて | |
| ターラヤン 2003-12-23 16:11:42
[返信] [編集] 返事が遅くなりましたが・・・。 > * 「620Xi−S」という機種ですが、価格がA−VX込みで定価ベースで82万円 、保守料金3700円/月という話でした。 > スタンドアロンというわけではなさそうなので、純粋なPCサーバベースと比べてもかなり魅力のある価格だな、と思いました。(それともこれはスタンドアロンしかだめなモデルなのでしょうか?? ターラヤンさん、ご存じでしたらお教えください!!) 江須扇さんの書いているように、Windows側のOSがWindows2000Professional/WindowsXPとクライアント系になっています。詳しくは忘れてしまいましたが、クライアント系OSだと、サーバ系のOSと比べて、接続できるコンピュータ台数の最大数が少なかったような気がします。 それからお安くするためか、UPSやバックアップ装置が標準で付いていない、あまり使わない?ハードが付けられない、あまり使わない?A−VXの機能がはずされている点が気になるところでしょうか。 でもITOS/A−VXのソフトは問題なく使用できるはずですし、ハードについてもたとえ使えないものがあっても代替の接続方法や装置があるので、普通に使う分には問題ないと思います。 S3100やS7200のリプレースで、あまり新規の機能を使わずに、今まで使っていたソフトをそのまま使おうという人向けのような気がします。(あくまでも個人的な意見です。) ついでですが、 >例えば、700シリーズの時代には、ウィルスチェックのソフトひとつとっても、種類が少なくて困りましたものね。。 S7200やS3100ならば、(クライアントにPCを使っていなければ)、コンピュータウィルスとは無縁ですよね。 600シリーズもA−VXだけならウィルスとは無縁なのですが、Windows側が影響を受けてしまいます。 | |
| 620xi−sの件 | |
| 江須扇 2003-12-23 3:06:48
[返信] [編集] > * 「620Xi−S」という機種ですが、価格がA−VX込みで定価ベースで82万円 、保守料金3700円/月という話でした。 > スタンドアロンというわけではなさそうなので、純粋なPCサーバベースと比べてもかなり魅力のある価格だな、と思いました。(それともこれはスタンドアロンしかだめなモデルなのでしょうか?? ターラヤンさん、ご存じでしたらお教えください!!) 正確なことは解りませんが、 Express5800/610xx WNT、W2KのWorkstation Express5800/620xx−s WNT、W2KのWorkstation、XPprofessional Express5800/620xx以上 WNT、W2K、2003Server となっています。 610は純粋はスタンドアロンですが620xx−sはWSは接続可能と思います。 但しWinOSがサーバーでないのでその制限があると思います。 たとえは、RDB/FILEアクセスキット等がマルチでは使えないと思います。A−VXだけのマルチワークと思いました。 正確にはやはりNECに確認してください。 | |
| 従来型「オフコン」から新「600xiシリーズ」への移行検討の方へ | |
| EXCHANGE 2003-12-17 16:33:27
[返信] [編集] * ターラヤンさんが「現物を見た人はいませんか?」とおっしゃっておられましたが、残念ながらわたくしもまだ600Xiの現品にはお目に掛かっておりません。 * 機能、性能に関する(主に営業担当からの)説明と、カタログなどより判断して、従来型の「オフコン」から「600Xi」に移行を考えておられる方(考えておられる会社)に参考になりそうなこと、気づいたことなどを書いてみました。 * S7200(もっと古い3100/AXX)などからの移行検討の場合。。。 まず、図体(筐体とも呼ばれています)があまりに小さくなっていますので、ちょっとショック(落胆?)をおうけになるでしょう。 そのかわり、正直言って移行後は「あまりにも処理速度が速くなった」のに驚かれると思います。とくに専用端末などをお使いだった方には隔世の感があるでしょう。価格もかなりお安くなっていますし、なによりも「保守料金」が安いのがうれしい。 以前の経験では、7200/80を使っていた会社(端末50台程度)でも640で十分OKでした。「再リースできるので、まだまだ使うんじゃ!」という社長さんもおられるかもしれませんが、「7200保守料金」と「新600+新保守料金」を比較すると、買い換えてもさほどUPしなかったりするので、よく研究してみてください。 それに出来ることは、格段に拡大していますし。。(特にオープン連携) このパターンは、「○○屋の牛丼」ではありませんが「安い、速い、うまい」にきっと満足されるでしょう。 * 700シリーズからの移行を検討している方の場合。。 スタイルは基本的には同じなのですが、INTELベースになったために、使える道具(ハード、ソフト)が格段に多くなっています。例えば、700シリーズの時代には、ウィルスチェックのソフトひとつとっても、種類が少なくて困りましたものね。。 それにやはり、小型化、スピードアップがすばらしいです。 あと、オープン連携機能が充実しています。700シリーズの頃は、NT上で動かすのが精一杯という感じでしたから。。 それに比べると、600系(特にAi以後)は、A−VXを動かすのにかなり余裕があるみたいです。そのため実際に使える連係機能がかなり増えています。 ** (便利だな、と思った機能について) ** (1) BizReporting V2.0 A−VXからの印刷を編集して、windowsの各種フォントを利用したり、図形、バーコード、ロゴ、イメージデータ、等を貼り付けて印刷できる機能。Webブラウザでの帳票参照も可能で、インターネットでの帳票配信も出来ます。 従来の印刷パスからデータを取得して利用できるみたいです。(アプリの修正なしでレイアウト変更可能、インストールとSGのみで利用出来るようです) ホスト系のコンピュータは「フォント」「イメージ」など、帳票の表現力の点で欲求不満があっただけに、この機能は私としては一番うれしい機能と思いました。 (2)A−VX/APアクセスオブジェクト V2.0 windowsアプリケーションからA−VX上のCOBOLアプリケーションを起動したり、データのやりとりが出来ますので、これを使ってモバイル端末(iモード端末)からインターネット経由で在庫問い合わせ、注文入力などが出来るでしょう。(WEBサーバ、セキュリティを考慮した環境、データやりとりのためのアプリ追加は、もちろん必要ですが。。) ほかにもたくさんありますが、この辺で。。 最後に一つだけ気づいたこと。 * 「620Xi−S」という機種ですが、価格がA−VX込みで定価ベースで82万円 、保守料金3700円/月という話でした。 スタンドアロンというわけではなさそうなので、純粋なPCサーバベースと比べてもかなり魅力のある価格だな、と思いました。(それともこれはスタンドアロンしかだめなモデルなのでしょうか?? ターラヤンさん、ご存じでしたらお教えください!!) * なお以上は、あくまでも私の個人的な感想ですので、「参考」とお考えください。 詳しくは代理店などの営業担当者によくご確認ください。 | |
| Re: NEC COBOL の違い 補足 | |
| ターラヤン 2003-12-17 16:02:28
[返信] [編集] 回答ありがとうございます。 > 話は長くなりましたが、OSは別物でCOBOLソース互換ということで、再コンパイルは必要でした。 > ファイル管理等は互換性があったので、データやプログラムはハードウェア的に同一機器があれば、FD等で移行はできました。 > ただし、ISAMファイルはありませんでしたので、あくまで順編成ファイルとしての移行でした。 ITOS以前と以後では、プログラムはソース互換。 ITOS以降現在までは、バイナリ互換。 データはずっと使えたということですね。 他社のオフコンは、OS名称が変わると、ソース互換なので再コンパイルが必要ということがありましたが、NECのはITOS->A−VX10・・・->A−VX01では再コンパイル必要なし。 最下位モデルから最上位モデルまで同じOSなので、モデルを変えたために再コンパイルする必要もなし。 ただし、NECのオフコンは、かつてS3100系とS3050系があり、その間は(だいたい)ソース互換なので、シングルアーキテクチャとは言えない。(操作方法などの統一をしようとはしていた。) 今他社のオフコンについて書こうと思い、情報を整理しています。 他社オフコンは、新モデルや新OSになったときに、前モデルと比べて、どの程度互換性があるのかというところをまとめていたのですが、逆にNECのオフコンは昔はどうだったのかと思い質問しました。 (私のところにある先人の残した資料は、基本的なことは知っていることを前提に書かれているので、当時を知らない私にはよくわからないところがあります。これがわかれば、NECオフコンの歴史の項をもっと詳しく書くことができるのですが・・・。) | |
| Re: NEC COBOL の違い 補足 | |
| 江須扇 2003-12-17 3:39:24
[返信] [編集] > ところで私の資料では、OS−4のCOBOLは、ITOSになった時に再コンパイルしなければならなかったようですが、それで間違い無いでしょうか。 はい、間違い有りません。 > つまり、OS−4とITOS−4の間では、バイナリレベルの互換は無かったということでしょうか? 元々、1973年にオフコンが発表されたとき、それ以前のNEAC1240はCOPCODERというアッセンブラーが基本で機械語も直接わかるような10進のワードマシンでした。 つまり、OSはまったく有りませんでした。 旧100が出た当時はOSと言う表現では無く、MONITORと称して、電源を入れたら読み込み日付と時間を入れていました。 説明ではハードでもソフトでもないファームウェアの読み込みと言われました。 その後、他社との対抗上かっこ悪かったのか、後半ではOS−4という名称にしましたが、ITOSに比べたら比較になりません。 ただ、ファイル管理やエラー表示また、SORTやFLCNVなどのユーティリティは一応できておりました。 ユーティリティのパラメータの入れ方は踏襲しておりました。 話は長くなりましたが、OSは別物でCOBOLソース互換ということで、再コンパイルは必要でした。 ファイル管理等は互換性があったので、データやプログラムはハードウェア的に同一機器があれば、FD等で移行はできました。 ただし、ISAMファイルはありませんでしたので、あくまで順編成ファイルとしての移行でした。 > ご存知でしたら教えてください。 | |
| 新しいExpress5800/600シリーズの話題は? | |
| ターラヤン 2003-12-16 17:12:04
[返信] [編集] 新しいExpress5800/600シリーズを見た人はいないのでしょうか。 iEXPO2003には展示してあったそうなので、もし行かれた方がいらっしゃったら、どんな感じだったのか教えてください。 本当ならば、私が行ってネタにするべきだったのですが、仕事が忙しくて行くことができませんでした。 この新機能があったとか、何か話題があると良いのですが。 12月に入ってから、急にサイトのカウンタが毎日60〜70ぐらい回るようになったので、もしかすると新しいExpress5800/600の情報を求めて来ている方がいらっしゃるのではないかと思ったので。 | |
| Re: NEC COBOL の違い 補足 | |
| ターラヤン 2003-12-16 15:21:17
[返信] [編集] >>1980年JIS COBOLに準拠ということですがその後の表現でもANSI74COBOLですね >>ITOS COBOL85 1987年JIS COBOLに準拠ということですがその名の通りANSI85COBOLですね(1987?現在) コボラーの方なので、おそらく知っているのでしょうが・・・、 COBOLのことをあまり知らない方も見ているかもしれないということで、 COBOLの仕様は、コダシルのCOBOLが決まった後に、ANSIのCOBOLがそれを参考に決定され、次にISO、JISと前のものを参考に決まっていくので、ANSIとJISでは数年の差があります。 ところで私の資料では、OS−4のCOBOLは、ITOSになった時に再コンパイルしなければならなかったようですが、それで間違い無いでしょうか。 つまり、OS−4とITOS−4の間では、バイナリレベルの互換は無かったということでしょうか? ご存知でしたら教えてください。 | |
| NEC COBOL の違い 補足 | |
| 江須扇 2003-12-12 3:44:52
[返信] [編集] COBOLの古いマニュアルがあったので補足します。 OS?4 COBOL4E 旧100時代です(1973〜78) ITOS COBOL4 旧100の継承用(1978〜?) ITOS COBOL 当初は”高級”がついていた(1984〜?) 1980年JIS COBOLに準拠ということですがその後の表現でもANSI74COBOLですね ITOS COBOL85 1987年JIS COBOLに準拠ということですがその名の通りANSI85COBOLですね(1987〜現在) COBOL4のコンパイラーは”や=の代替で旧100が使っていた@や#を可能としていました。 COBOLのコンパイルのパラメータ COMPILE MODE; CMO=NATIVE・・・COBOLモード COBOL4・・・COBOL4互換モード COBOL85のコンパイルのパラメータ COMPILE MODE; CMO=NATIVE・・・COBOL85モード COBOL74・・・COBOL互換モード と言うことで、3つのCOBOLは一世代前をオプションで利用可能としていました。 | |
| Re:x3:A−VXのパッケージ | |
| 江須扇 2003-12-11 14:48:36
[返信] [編集] > * 高級COBOL???? そんなのってあったのですか。。 > 知りませんでした。 COBOL4はA−VX以前の旧100(赤100)のOS4のCOBOL仕様を継承したものだったと思います。1978年頃の話なので、曖昧な記憶です。 なにせそのCOBOLはIF命令もGOTO命令ぐらいしか書けなくて二重のIFが出来なかったと思います。パックデータも使えなかったと思います。 > * COBOL4については、リコー関係の方が使っているのを見たことはあります。漢字のところが””(ダブルクウォーテーション)に囲まれたアルファベットなどのコードが並んでいて分かりにく?い!!という印象だけが。。 漢字は16進入力でした、リコーはこの時点ではカタカナ2文字で漢字ONOFFコードで囲むというわかりやすい方法でしたね。 しかし、逆にこの方法が後で1バイト2バイトの混在モードが使えないという足かせになりましね。 > * RICOMはACEPCRT(XX,XX)、DISPCRT(XX,XX) っていう画面入出力でしたね。 これはまさしく、リコーがNECと提携した時の旧100時代のCOBOL仕様を取り込んだものです。 > * 「高級COBOL」というのはCOBOL4、CBL85とどういう風に違っていたのでしょうか?漢字属性がNC””になったのはどの時点からでしょうか?? 高級COBOLはCOBOL4に比べて”高級”ということで、普通のCOBOLです。コンパイルモードにNATIVEモードとCOBOL4互換モードがあり、画面は互換モードはACEPCRT、DISPCRTが使えたと思います。NATIVEモードはSCREEN SECTIONだと思います。 COBOL85が出てからはただのCOBOLに名称変更したと思います。COBOL85のコンパイルモードで互換モードがこのCOBOLのことです。 85との違いはEND−IF等の85年仕様が使えないことです。 その他CRT−STATUSがCOBOL85ではHTAB(Return)とSKIPキーが違いますが、COBOLでは同じでした。 画面の動きが違ってしまうので、COBOLで作ったプログラムをCOBOL85でコンパイルするときは互換モードにする必要がありました。 その後の仕様強化はCOBOL85だけと思います。 例えば1バイト2バイトの混在入力MIXモード等や 副画面や矢印キーのCRT−STATUSが使えるようになったことなどです。 報告書機能や分類機能はCOBOLでもあったと思います。 RDB機能や日本語処理機能はどこまであったかははっきり覚えておりません。 > * 余談ですが、NCを使わず、””で囲んでオープンフィールドにすると、何か漢字の組み合わせによってうまく表示できない場合がありますね。 ひらがなの一部でコンパイルエラーになりましね。 > * さて、COBOL2002はA−VXに搭載される予定は全くないのでしょうか? オブジェクト指向や、例外処理なども出来るみたいです。 本気でA−VXを売るならCOBOL対応OSとしてサポートすべきと思いますがコンパイラーを開発する要員をNECは今でも抱えているのでしょうか? > >販売管理、生産管理など個別要素の多いシステムは個別システムで作られているかパッケージと称してもかなりカストマイズをいれているのでそのまま、A−VXで生き延びているというパターンが多いようです。 > * NECのオフコンパッケージというのは、もともとソースも提供されていたのですか? 日本事務器や大塚商会等の大手デーラーは自社パッケージを開発していたので、ソースは社内では自由にしていたと思います。 中小デーラーはメーカパッケージと称してSEA/I APLIKAが出てきたのですがこれはデーラーにはソースは提供されていたようです。 SEA/IはCASEツールですので部品提供というだったような 気もします。 その後のSuperAPLIKA 3SAPLIKAはソースは非公開でした。各社のデーラーパッケージはどこまでがパッケージでどこまでがプロトタイプかよくわかりません。そのデーラーの考え方で、エンドユーザーまでソースを公開した場合もあると思います。 > >しかし、個別に作るのであれば今でもCOBOLで作るA−VXには価値があると考えます > > * 私も同感です。「保守がしやすい」「確実に資産継承出来る安心感」それにオープン系と違って「いろいろ余計なことに煩わされずに業務分析、ロジックに注力出来る」等々。。 > > * 問題は、NECさんがA−VXに関する中長期の方針(ロードマップ)を明確に表明してくれたら。。ということです。 > A?VXを打ち切る場合でもそれとほぼ互換の「実行環境」を提供する予定である、とかそういった見通しがはっきりあればユーザさんも安心して「新規」を開発できるのではないでしょうか? > 今もところ、NECを「信じるほかない」という。。。 同感です。 | |
| Re: A−VXのパッケージ | |
| ターラヤン 2003-12-11 11:54:21
[返信] [編集] >>販売管理、生産管理など個別要素の多いシステムは個別システムで作られているかパッケージと称してもかなりカストマイズをいれているのでそのまま、A−VXで生き延びているというパターンが多いようです。 > >* NECのオフコンパッケージというのは、もともとソースも提供されていたのですか? 昔のことなので詳細は忘れましたが、いろいろな処理が部品化というかサブシステム化されていて、何十種類もの部品の中から適したものを積み木のように処理を組み上げていくと。 さらに金額や個数などの桁数など細かい部分はパラメータで指定できるようになっていたはず。 (建前上は)ヒアリング用の用紙があって、それに従って質疑をしていけば、自然とできるというもの。 すっかり忘れたので、もしかしたらNECのパッケージではないかもしれません。 もちろんパッケージソフトを作っている会社によって、仕組みは千差万別でかなり自由度の高いものから、ほとんど変更の余地の無いものまでいろいろありました。 インターフェース部分の仕様が公開されていて、出力部分(伝票とかです)は簡易言語を使って自分で作るのもあったはず。 | |
| Re: A−VXのパッケージ | |
| EXCHANGE 2003-12-11 9:54:03
[返信] [編集] * 高級COBOL???? そんなのってあったのですか。。 知りませんでした。 * なにせ、以前申し上げたように、NECのCOBOLに関しては、CBL85しかやったことがありませんでしたので。。 * COBOL4については、リコー関係の方が使っているのを見たことはあります。漢字のところが””(ダブルクウォーテーション)に囲まれたアルファベットなどのコードが並んでいて分かりにく?い!!という印象だけが。。 * RICOMはACEPCRT(XX,XX)、DISPCRT(XX,XX) っていう画面入出力でしたね。 これは、後でOS2上で実行環境になったとき(735D等)も、同じようなサブルーチンが提供されていました。 でも、AS/400(RICOH−i740)では画面ファイルでの入出力でしたのでちょっと操作上の不統一がありました。 * 「高級COBOL」というのはCOBOL4、CBL85とどういう風に違っていたのでしょうか?漢字属性がNC””になったのはどの時点からでしょうか?? * 余談ですが、NCを使わず、””で囲んでオープンフィールドにすると、何か漢字の組み合わせによってうまく表示できない場合がありますね。 * さて、COBOL2002はA−VXに搭載される予定は全くないのでしょうか? オブジェクト指向や、例外処理なども出来るみたいです。 >販売管理、生産管理など個別要素の多いシステムは個別システムで作られているかパッケージと称してもかなりカストマイズをいれているのでそのまま、A−VXで生き延びているというパターンが多いようです。 * NECのオフコンパッケージというのは、もともとソースも提供されていたのですか? >しかし、個別に作るのであれば今でもCOBOLで作るA−VXには価値があると考えます * 私も同感です。「保守がしやすい」「確実に資産継承出来る安心感」それにオープン系と違って「いろいろ余計なことに煩わされずに業務分析、ロジックに注力出来る」等々。。 * 問題は、NECさんがA−VXに関する中長期の方針(ロードマップ)を明確に表明してくれたら。。ということです。 A−VXを打ち切る場合でもそれとほぼ互換の「実行環境」を提供する予定である、とかそういった見通しがはっきりあればユーザさんも安心して「新規」を開発できるのではないでしょうか? 今もところ、NECを「信じるほかない」という。。。 | |
| A−VXのパッケージ | |
| 江須扇 2003-12-11 3:44:19
[返信] [編集] > はじめまして、江須扇さん。それにしても、皆さん、 > マニアックですねぇ(笑)そういう私も、まだ、 > 懐かしい、あのCOBOL4を使用しています。 返信ありがとう御座います。 COBOL4ですか。 DISPCRTとACEPCRT命令があるやつですか? RICOHはCOMPOSシリーズのCOBOLはこれにならって 画面の命令をカストマイズしてあったと思います。 その後、NECは高級COBOL、COBOL85と進化したと思います。 > 表紙のオフコン関係情報欄に「iシンポ」の記載がありましたね。 > ご意見がありましたら…というので、下記の内容でNECに投げて > みました。 今回のA−VX01のWeb頁の下の方を見てもEXPLANNER/Aという SEA/IAPLIKA → SuperAPLIKA 3SAPLIKA (ここまでA?VX) その後のAPLIKA(Winodws版の名前は忘れました)からWindows対応になりその後継となるパッケージが載ってますね。 つまりNECはパッケージはWindows側のOSで動かせという事のようです。 財務会計、給与計算等は切り出してパソコンパッケージに切り替えている場合が多いようです。 販売管理、生産管理など個別要素の多いシステムは個別システムで作られているかパッケージと称してもかなりカストマイズをいれているのでそのまま、A?VXで生き延びているというパターンが多いようです。 完全固定パッケージ(カストマイズできない)システムを選択肢とする場合は、やはりオープンシステムのパッケージを選ぶしかないようです。 しかし、個別に作るのであれば今でもCOBOLで作るA−VXには価値があると考えます。 (作れる人が少なくなってる現実はありますが・・・・・) 以上 > > *―――――――――――――――――――――* > > A―VXアプリケーションパッケージの不足とA―VXの今後について > > 弊社では自社開発品、パッケージソフトの両方を使用してきました。数年前から、リストラ等で要員が減り、自社開発が難しくなってきました。ディーラーのパッケージソフト購入を検討するにもA―VX対応のパッケージは姿を消しつつあります。また、以前にも指摘されたようにA―VXに精通しているSEも姿を消しつつあります。他のユーザーの方で、パッケージを使用されている場合、どういうところから入手されているのでしょうか。弊社で現在使用のパッケージは20年以上前に購入したもので、必要に応じて自社で修正を繰り返してきました。今後、人手不足もあり、このような修正も出来なくなってくると思います。他の方々も同様な使い方をされているのでしょうか。 > > 長年使ってきたA―VXは、使用し易く安定度にも満足していますが、今後、会社の世代交代を考えた場合、業務パッケージが入手できなくなってくると、PC系への前面移行も検討課題になってきます。NECとして、A―VX系の業務パッケージの供給については、どのように考えているのでしょうか。今後、A―VXユーザー維持、拡大を意図しているなら最も基幹的な部分ではないでしょうか? > それとも、A―VXの拡販や維持は意図せず、ただ現ユーザーの現時点での便宜のみを重視しPC連携のミドルウエア等のツールを提供することに徹していくのでしょうか。 > A―VXに対して、どのような方向性を考えているのか…NECの考えをお聞かせください。 > > *-------------------------- > > すると、、会場ではお答えできる内容ではないとのことで、 > 後日、os開発部門の方が見えました。 彼らのAVX > に対する思いもわかりました。 > が、、、やはり、というか、拡販する意図は、会社的には > あまり積極的ではないような感じでした。考えてみると > オフコン全盛期には、いろんな講習会があったけど、今 > は、そんなもの全くないんじゃないでしょうか。 > 後継者を育てるにも、ちょっと難しい状況ですね。あと > 10年、20年後にどうなってしまうのか。。自然消滅 > してしまうのか。ちょっと不安です。その頃には、もう > 私もいないでしょうが(笑) > 話の中で出たのですが、やはりというか、新規にAVX > を買うユーザーはいないそうです。現状、他社のオフコン > からの乗り換え。PCサーバーにしたけど、問題があって > 戻ってきた客とのことでした。 > > つまらない話をくどくど書いてしまいました。おつきあい > ありがとうございました。 > | |
| Re:x3:Windowsアプリ立ち上げPG | |
| EXCHANGE 2003-12-10 19:55:31
[返信] [編集] * A−VX用パッケージソフトについて > 弊社では自社開発品、パッケージソフトの両方を使用してきました。数年前から、リストラ等で要員が減り、自社開発が難しくなってきました。ディーラーのパッケージソフト購入を検討するにもA―VX対応のパッケージは姿を消しつつあります。また、以前にも指摘されたようにA―VXに精通しているSEも姿を消しつつあります。 * 私はAVXでのパッケージというのは使ったことがなかったので、「最近少なくなっている」ということに全く気づきませんでした。 * 困ったことですね。。 でも、パッケージを開発する人から見ればいわゆる「オープン系」で作った方が市場が広いですから、どうしてもそうなっちゃうんでしょうね。 何でするか?ときかれたら、かくいう私でも、AVXでするのは「前からA−VXの顧客」相手であって、新規は「オープン系」で作ろうと思いますもんね。。 * こういう場(オフコン練習帳)を使って「A−VX版オープンソース運動」をやってはどうでしょうか? 自社で開発されたソフトを基にして公開してもかまわないという作品も出てくるかも。。 * あと、こういう場でいろいろ技術情報の交換が出来ればきっとすばらしいでしょうね。 | |
| それはそれでいいのでは。。(等身大のAVX) | |
| EXCHANGE 2003-12-10 19:15:49
[返信] [編集] * はじめまして、CBL4さん。 * すごいですね、わたしはCOBOL85しかやったことがありません。(そのころはRICOMしてましたので。。) * NEC(供給側)のAVXに対する雰囲気なども、興味深く読ませて頂きました。 それと、会場のその場で確固たる見解を出さずに、個別面談で本音の説明に来られるところも、やはり「隠れ」っぽい感じでしょうか?! * 私は、IBMのASもかじったことがあるので、思うのですが、「ホスト系のオフコン」で最後まで残るのはきっとIBMだけでしょう。メーカ側の熱意も違いますし、実際OS、ユーティリティの作りの深さと先進性が全く違います。なんと言っても「ホスト系」の元祖です。そこに老舗の実力と意地を感じます。 * もはや(AVXも含めて)日本のオフコン(=中規模ホスト系コンピュータ)の時代と役割は過去のものとなったと思います。 * OSの開発や拡張には多額の「予算」が必要でしょうし、その予算は製品がどんどん売れてこそまかなえるという、現実的な問題もあるでしょう。 それにもまして、NECの開発のトップの方々から見れば、 現在の世界的OS技術レベル、将来的技術動向と比較して、 「AVXという技術が」どの程度のレベルのものか「見えてしまう」のではないでしょうか? * ただひとつ、私の狭い経験から書かせて頂きたいのは、 (いろんなお客様のシステムを作らせて頂きましたが) 中小のお客様ほど、ASよりもAVXの方が「操作もわかりやすく、より好きだ」とおっしゃられた、という事実です。 * もともとAVXは頭でっかちなOSではなく、日本の中小企業を想定した「実際的な」製品であったと思います。 その考え方は、今のAVX4,AVX01などにも引き継がれていて、「過去のオフコン資産」を生かしつつ「オープンな世界」と連携していく、「安い費用」で「慣れた操作性」の中で、「新しいもの」を容易に取り込んでいく、やり方ではないでしょうか? (実際、現在でもAVX4で作ったシステムはコストパフォーマンスから見て「実際的でけっこういける」という感じですから。。) * 私は今考えると、AVXをWinServer上に乗せる(windowsの中へ包み込んだというべきか?)というNECのやり方の中に、なにか一種の(日本的)「やさしさ」をすら感じてしまいます。 * もう、「時代は終わった」のですが、「中小企業、とりわけ、会社は一定規模ではあっても、IT専門スタッフのいない企業ではまだ必要とされている部分」もかなりあります。 * NECは、AVXをwindowsのなかに入れることで、 「顧客が実際に必要とする限り生き延びさせよう」としているように見えます。 * やがて「一人去り、二人去り」していつかは消えていくのでしょうが、それはそれでいいのではないでしょうか。 * それよりもNECが現在のAVXユーザを、少しずつ「新しい世界」へ「導いて」いってくれればよいと思っています。 劇的ではなくっても少しずつ改良をしながらソフトランディングさせてくれればよいのです。 顧客にとって重要なことは、「長年NECを使ってきたが、今後もNECについて行けば間違いない」と感じるられることなのでしょう。 | |
| Re:x3:Windowsアプリ立ち上げPG | |
| CBL4 2003-12-10 7:54:59
[返信] [編集] はじめまして、江須扇さん。それにしても、皆さん、 マニアックですねぇ(笑)そういう私も、まだ、 懐かしい、あのCOBOL4を使用しています。 表紙のオフコン関係情報欄に「iシンポ」の記載がありましたね。 ご意見がありましたら…というので、下記の内容でNECに投げて みました。 *―――――――――――――――――――――* A―VXアプリケーションパッケージの不足とA―VXの今後について 弊社では自社開発品、パッケージソフトの両方を使用してきました。数年前から、リストラ等で要員が減り、自社開発が難しくなってきました。ディーラーのパッケージソフト購入を検討するにもA―VX対応のパッケージは姿を消しつつあります。また、以前にも指摘されたようにA―VXに精通しているSEも姿を消しつつあります。他のユーザーの方で、パッケージを使用されている場合、どういうところから入手されているのでしょうか。弊社で現在使用のパッケージは20年以上前に購入したもので、必要に応じて自社で修正を繰り返してきました。今後、人手不足もあり、このような修正も出来なくなってくると思います。他の方々も同様な使い方をされているのでしょうか。 長年使ってきたA―VXは、使用し易く安定度にも満足していますが、今後、会社の世代交代を考えた場合、業務パッケージが入手できなくなってくると、PC系への前面移行も検討課題になってきます。NECとして、A―VX系の業務パッケージの供給については、どのように考えているのでしょうか。今後、A―VXユーザー維持、拡大を意図しているなら最も基幹的な部分ではないでしょうか? それとも、A―VXの拡販や維持は意図せず、ただ現ユーザーの現時点での便宜のみを重視しPC連携のミドルウエア等のツールを提供することに徹していくのでしょうか。 A―VXに対して、どのような方向性を考えているのか…NECの考えをお聞かせください。 *-------------------------- すると、、会場ではお答えできる内容ではないとのことで、 後日、os開発部門の方が見えました。 彼らのAVX に対する思いもわかりました。 が、、、やはり、というか、拡販する意図は、会社的には あまり積極的ではないような感じでした。考えてみると オフコン全盛期には、いろんな講習会があったけど、今 は、そんなもの全くないんじゃないでしょうか。 後継者を育てるにも、ちょっと難しい状況ですね。あと 10年、20年後にどうなってしまうのか。。自然消滅 してしまうのか。ちょっと不安です。その頃には、もう 私もいないでしょうが(笑) 話の中で出たのですが、やはりというか、新規にAVX を買うユーザーはいないそうです。現状、他社のオフコン からの乗り換え。PCサーバーにしたけど、問題があって 戻ってきた客とのことでした。 つまらない話をくどくど書いてしまいました。おつきあい ありがとうございました。 |
| 新規投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ |
BluesBB ©Sting_Band