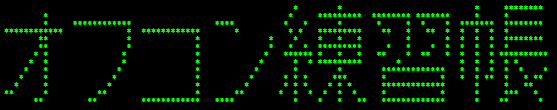NECのオフコン情報掲示板(いろいろ)
| NECのオフコンに関しての最新情報、面白い話、昔の思い出、何でも自由に書いてください。 |
| 新規投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ |
| Re:(600は「買い」だ!):私も同じ考えです。(追加) | |
| 江須扇 2003-10-13 3:28:53
[返信] [編集] A−VXのメリットとして、 A−VX COBOL が解らないとできない というのがメリットと思います。 つまり、セキュリティの観点から知らない人にはデータベース構造、プログラム構造がわからないというのが良いと思います。 正しく、上司から部下、先輩から後輩へ技術伝承してこそ使えるのです。 これが、いい意味での伝統の継続と思います。 基幹業務は社内規定(基準)に準じドキュメントを残し継承されるべきと思います。 | |
| Re:(600は「買い」だ!):私も同じ考えです。(賛同します) | |
| 江須扇 2003-10-12 11:39:12
[返信] [編集] EXCHANGEさん、こんにちは、 (600は「買い」だ!)に賛同します。 私の訳のわからん投稿より説得力がありますね。 ターラヤンさん、こんにちは、 私の訳のわからん投稿にはRESつけづらかったですね。 ただ、私もお2人まけないぐらいA−VXをこよなく愛しておることをご理解ください。 3人しか出てきませんが、100倍、いや1000倍くらいの方が見ていると思います。 この意見がきっとサイレントマジョリティーの方の賛同を得られると確信しております。 NECさん、最初の600シリーズを利用している方はもう6年経ちます。 そろそろ、マイナーチェンジでは無く”サプライズ”あるフルモデルチェンジをして欲しいですね。 次回はもっと簡単な投稿にします。 乞う、御期待(といってもたいしたことはありませんが・・・・) | |
| 私も同じ考えです。(続き) | |
| ターラヤン 2003-10-11 13:58:22
[返信] [編集] 先ほどは、考えをまとめずに書いてしまったので、何を言いたいのかよくわからない文章になってしまいましたが、 補足すると、EXCHANGEさんの言う通り、 2,3ができるということは、基幹系は今まで通りA−VXで、情報系はWindowsのソフトでということができます。 (実際NECの方もそう言っているようです。) 600シリーズは、Windowsサーバでもあるので、今もし管理者がWindowsのことをあまり知らなくても、Windows管理のノウハウも自然と付いてくるし、 逆に今の若い人はWindows’しか’知らない場合もあるが、Windowsから入ってA-VXへなら受け入れやすい。 これもEXCHANGEさんの言う通り、A−VX基幹系+Windows情報系にしておけば、将来いざオープン系へ移行という時も(今と比べて)楽になるはず。 600シリーズはWindowsサーバなので、オフコンのことを知らないようなソフトハウスもリプレースしやすいでしょうし。 EXCHANGEさん、江須扇さんなどと同じように、私もオフコンはいいと思います。 でも今の世間の流行/傾向はオープンの方ですから、オープンにするにはどうしたらいいの?という質問が多いのも仕方がないことだと思います。 オープンにできるよう道を付けておいて、最後の判断は当事者に任せ、方向が決まったら、その方向になるべく簡単に行けるようにしておくことが大切だと思います。 p.s. 私が書いたものを読み直して見て、 何か偉そうなことを書いていますが、実際自分自身を振り返ってみると、全然書いているようなことはしていません。 私の行動は書いていることとは正反対、いつもその場その場のやっつけ仕事ばかりで、恥ずかしい限りです。 昔の技術に胡座をかいて、A-VX4の新しい機能は全然使わず知りもせず・・・。最近は、心を入れ替えて勉強しています。 | |
| 私も同じ考えです。 | |
| ターラヤン 2003-10-11 13:17:44
[返信] [編集] いつもお話ありがとうございます。オフコンに対する熱い思いが伝わってきます。 S3100やS7200を今も使用されている場合、これからもオフコンを使い続けるにしても、 Windowsなどのいわゆるオープン系といわれているものにしようとする場合にしても、 Express5800/600シリーズにする利点は多いと思います。 Express5800/600シリーズならば、 1.今までのソフト/データがそのまま使用できること。 2.Windows2000のサーバでもあること。つまりWindowsのソフトも使用できる。 3.A-VXからWindowsへデータを渡すPathがいろいろ用意されていること。 1は当たり前(Windowsはこの当たり前のことすら、なかなかやってくれないのですが、)のこととして、 2と3は結構重要だと思います。 2のWindowsのソフトが動くということは、NECのHPにも明確に書かれていませんし、 案外知られていないという気がします。 Express5800/600シリーズ上では、マイクロソフトのEXCHANGEでもSQLServerでもIISでもWORD、EXCELでも、 あるいはDB2、NOTES、ORACLE、SendMail、よくテレビでCMをしている○○奉行とか××大臣とか、 町のパソコン屋で売っているWindowsソフト、インターネット上のフリーソフトだって動きます。 (既に同じような業務ソフトが載っているオフコンに、さらに○○奉行を載せてどうする、という話もありますが、 あくまでもWindowsソフトなら何でも動くという例ということで出しただけです。 当然、○○奉行を使うのならば、600シリーズにする必然性がない。) 3は、A-VXとWindowsの間でデータ交換が簡単ということもありますが、 将来オープン系に移行するときにも、S3100やS7200と比べて楽にデータを移せる。(あくまでも”比べて”という話です) これからどうするかまだ決めていないというのならば、一旦、600シリーズにしておいて、 それからこのままオフコンとして使用し続けるか、オープンにするか、決めるという手もあります。 | |
| (600は「買い」だ!): その3 「未来資産」構築のために | |
| EXCHANGE 2003-10-10 11:57:10
[返信] [編集] * 「次の一手」を考える前に、 ちょっと寄り道して、 「どうして、このような旧式な構築法が使われたのか?」という点を押さえておきましょう。 * それは、なにより「2000年問題」の裏に存在した「真の理由」と同じようなものです。当時のコンピュータのキャパシティがあまり大きくなかったための「容量節約」です。 (おまけ):現在かかっておられるSEさんと話をして、「こっちの方が容量が節約できるから(そうした)。。」というせりふがあまり頻繁にでるような方だったら、ちょっと要注意ですね。 * 小さいキャパで、きついお客の要望を何もかも一度にやってしまおう! という涙ぐましい努力が生み出した「芸術(アート)」でもありました。(今でも、そういうことが「プロ的」な腕だ、という信念を持っておられるSEさんがおられます。そういう方は概ね、ゲイツさんの容量無駄遣い垂れ流し型のOSに非常に嫌悪を感じられるようです) * しかし、「わかよたれそつねならむ」 時は流れ、時代は移り、コンピュータの容量問題は大きく改善されました。(ひとり「オフコン」だけが例外ではない。。) * 現在の「オフコン」(例えばNEC Express5800/600シリーズ)では、 「CPUのパワー、メモリの量、ディスクの容量などは十分なほど用意されており、必要ならさらに「安価」に増設できる。」 のです。 なんといっても、これは「Windows2000サーバですから。。」 * そこで、本題に戻りますが、私が言いたいのは こうした「プア」なシステムこそ再構築されるべきだ!! ということなのです。 (ただし、S7200以後のマシンをお使いの会社で「RDBサーバ」「SKYLINK」も使ったことがない、知らない、 と言う方は「再構築」の前に、まずこれらを「使ってみる」ことからお始めください。 この程度のこともやらずに、「パソコン系システムに替えて誰でも使える形にしたいから」などと比較評価されると、「オフコン」が可哀想ですから。。) * さて、「再構築」に際してどのようなことに留意すべきでしょうか? 以下、独断と偏見で。。 (1)まず、容量は十分用意されているし、AVXは元々あまり容量を無駄遣いしないOSなので、 「難しいプログラムテクニック」によって「容量節約」を計ったり、「スピードアップ」を計ったりすることは極力避け、 キャパが足りないときはどちらかというと「ハード」の増設で対応するような考え方を取る。 (ハードのパワーに依って解決を計る。「貧乏指向」から「リッチ指向」へ。 ハードの増設の方がソフトの変更より安上がり。 「ハード」はソフトに変更でき、「ソフト」はハード(硬い)であとから変更がしにくい。) (2)「基幹系システム」と「情報系システム」を考え方だけでなく実際のシステム上でも完全に「分離」するように設計する。 *基幹系マスタ上では残高に関わる項目のみ集計、更新する。いわゆる「何とか別、何とか別、実績マスタ」などは基幹系に作らない。基幹系データは残高を集計、更新するのに必要な分と、データ作成に参照する必要のある分などに絞る。 * レプリケーション機能をフル活用して、SQLサーバ(またはoracle)側に、「情報系DB」を構築する。 こちら側の定型ソフトはVB、ACCESS可。(それの方が長い目で安上がり。理由は後で説明)。 それから、こちら側は「別サーバ」の方がヨリ良い。これはふつうのPCサーバ。 (3)他社とのデータやりとりは、単純なバッチなら「パソコンソフト」でJCA、全銀などを使って、600シリーズのいわゆる「NT領域」に落とす。 複雑系は「Biztalk」を指向する。 営業所などへのデータ送信で従来S3100/10などを「受け」「受け後」に使っていた場合は、メール連携で「CSV添付」に切り替え、その先はVB、ACCESSで。 自社内の遠隔端末はVPNを使う。 いずれにせよ、極力「600シリーズの通信ボード」は使わないように心懸ける。 (4)上記を違和感なく操作できるよう「JOB起動ユーティリティ」などを使って、操作員に配慮する。 等々です。 あと、「RDBWAVE」(web版)というのはいかがでしょうか?(有償だが、安い!) (出来るだけ、AVX標準機能を使います。 オープンからAVXRDB、 AVXからオープンRDB といった斜め読みは極力避けます) * こうして、「基幹業務側」から「情報系的な部分」を分離すれば、 (1) 将来にわたって「基幹業務側」の変更はあまり発生せず、この部分の変更は最小限ですむ。(ディーラの「高い」見積もりを拝見する場面が減る) (2) いわゆる「情報系的な部分」は要望などが変化しやすく、ここらはVB、ACCESSなど「継続性が当てにならないツール」で作っても被害が少ない。それよりも表示、作表の「表現力」が大事な領域。 あと、この辺は「参照オンリー」に権限しとけば、「江須扇」様のページに出てきた「パソコンちょっとだけ知ってる的にわかプログラマ」を「活用」できる(こっちが「活用」してやるのだ)。 * かくして === 「未来資産」を創るのです!! === * 特に「基幹部分」に関しては、AVXは抜群に安定度も高く、そのCOBOLは今後の一貫した継続性が期待できます。 VBからVB.NETへの乗せ換えみたいな苦労を何度もしたい方は、どうぞ「MSで基幹を構築」なさってください。きっと 「 Do same with more 」 請け合いです。 * また、600シリーズは、AS400みたいにお高くないですし、それに、分離された「基幹業務側」のためには、そんなに大きな600シリーズでなくてもOKでしょう。 その分を「未来資産」の構築に当てるのです!! * それと、(これは、実はとっても「大事」な点!!) 旧オフコンを600シリーズに替えて一番驚くのは、きっとその「スピードの速さ」「処理能力の向上」だと思います。 「どうして今まで古いマシンを使い続けてきたのだろう?もっと早く600に替えれば良かった」と感じられるでしょう。 &&&&&&&&&& * 何?「AVXが将来も続くか心配」ですって? どんなものが将来も存続し続け、どんなものがそうでないのか、それは私にも分かりません。 でも、それを予測するのには、今までの「奴ら」の「行動(何をしたかの履歴)」を見ることでしょう。 MSのwindowsはある程度存続し続けてきましたが、その中身は大きく変わりました。そしてVB、ACCESSといった道具も当初とはすっかり変わってしまいました。 NECは、過去20年以上渡って「OS」「ツール」の継続性をほぼ完全に保証し続けてきました。 この辺あたりで判断するしかないでしょう。 それに見逃してはならないのは、「AVX」のバックで「通奏低音」のごとく販売されている「AVX実行環境」というやつです。 多分、枯れたOSである「AVX」を継続することは今後のNECにとってそんなにシンドイ仕事ではないでしょうし、それに従来のお客さんをあえて逃すという必要もないでしょうし、かりに 万が一「AVX」の存続が難しくなっても、 きっと「影の内閣」である「AVX実行環境」を充実させ、そこへの移行パスを用意してくれるような気がします。 * え、「それでもまだ心配」ですって??? どうしてもそのように思われる方には その時点で 「基幹業務側」を JAVAに置き換えることをおすすめしています。 すでに、「基幹業務側」は「分離」され、「最小化」されていますから、置き換えはきっと現在のシステムより「やりやすい」と思いますよ。。 (仕事が忙しくなってきたので、複数号をまとめてワンページに書いて、とりあえず 「完」 ) オソマツ。 | |
| (600は「買い」だ!): 追伸 | |
| EXCHANGE 2003-10-10 11:57:10
[返信] [編集] (追伸): 「今回JAVAに乗せ換え」 と言う場合は、もちろん現在の600シリーズでは不適当ですので、即その方法をということでしたら、しかるべき別のサーバをご用意ください。 今回600で構築し、将来ヤバくなったら「このようなルートもある」という意味ですので、念のため。 * SUNからSPARCの低価格サーバがでた!! うれしいな!! でも、やっぱり業務アプリは「A−VX」+「COBOL」の方が楽ちんですよね。。 * あんた、よっぽどゲイツさんが嫌いなの? いえいえ、私はほんとは「隠れMS」なんですよ?。 だって名前からして 「EXCHANGE」なんだもん。 | |
| (600は「買いだ!」):その2 「問題はどこに?」 | |
| EXCHANGE 2003-10-10 7:54:43
[返信] [編集] * 私は前提条件として端末1〜30台などと書きましたが、 1台(単独)でS3100/10(ディスク付)などをお使いの方は、まずパソコン(PC)の導入を検討すべきです。 本社などのオンライン端末としてお使いの場合でも、バッチ(一括)でデータを転送してお使いの場合でも、(本社側を「600シリーズ」に換えれば)原則としてPCで運用可能です。ただし、一括転送の場合は新たにACCESSなどで支店PC側のソフトを開発する必要があります。 また、単独で「財務管理業務」などを運用しているだけでしたら、パソコンパッケージなどで置き換え可能です。 * まあ、たいていの場合、上記のようなケースはあまりなくて、S7200/30(あるいは、S3100/30等)より上の本体装置+端末3台以上、というのがほとんどでしょう。 == そこで、問題点(2)の件です == <前回の書き込みを参照> * 「オフコン」だからデータがパソコン上でうまく利用できない、ですって??? 実は、このように思っておられる方(会社)が以外に多いのです。(AVXを使いこなしておられる会社の方は「うそ?」と思われるかもしれませんが。。) いろんな会社のコンサルをさせて頂いて、正直驚くのはこのパターンです。 それで「今度はパソコン系システムに替えようか」と迷っておられるわけです。 で、このパターン、よくよく調べてみると (1)なるほど、S7200あたりでBsepでパソコン端末は接続されており、「RDBサーバ」「SKYLINK」なども導入されているのですが、 (2)業務システム側が、旧式な構築法(ひどい場合、ファイルベースの時代の設計法)で出来ており、 (3)「EXCEL」などに数字を取り出しても、取り出したい「概念」(データ分析で要求されている集計条件、分類基準、期間)と合っていないため実態とズレがでてしまう。結局、他の出力リストを見て別途手で集計した方がマシ。 と、いう場合が圧倒的に多く見られました。 * 「ここんところ、こういう風な数字は取れないの?」とシステムを構築しているところに訊ねると、「う〜ん、出来ますけど、ん万円(ん>100だったり)」 * で、 「オフコン」はだめだ、パソコンシステムだったらこんなことははじめからうまく取り出せるのでは。。となるわけです。 * 要するに、このような問題を持っておられるのは、 (1)比較的早い時期(古い時代)から「オフコン」を導入されてきた(以前には先進的な)会社に多く、 (2)ハードを何度か買い換えても「オフコン」が、なまじそのままのソフトが次に継続使用出来たために、システムを現代化するということが取り残されてしまった、 というものです。 * このような場合、「次の一手」はどのようなものでしょうか? (続く) | |
| Re: オープンでもオフコンでも同じと思います。 | |
| 江須扇 2003-10-6 13:46:37
[返信] [編集] オープンは誰にでも使えるというのは、Windows系のGUIが簡単で操作が簡単だという事に代表されていると思います。 しかし、これが錯覚と思います。 パソコンデータベースソフトで簡単なシステムが組めたという事で、 独学でオープンシステムの基幹業務が作れるとはとても思えません。 キッチリと基幹業務を長期にわたって利用できるシステムとして構築するのは、オープンでもオフコンでもそれなりの手間隙はいっしょと思います。 また、その開発要員の能力も業務システムの開発の為のソリューション能力は一緒と思います。それなりの教育を受け勉強は必要でその担当者の努力も必要で手抜きではできません。 でも、極端な話、パソコンのワープロが使えればコンピュータ使えると錯覚し無謀にもなにも考えずシステムを作っている人がいるのは驚きです。 PCのリセット、リブート文化の考え方で、次のシステムもまた一から最新技術で作れば良い。と言う考え方と 一度作ったシステムはなるべく継続して使いその修正保守を容易にするというオフコンの考え方は 古い新しいではなく文化の違いと思います。 | |
| Re:我が亡き後に洪水来たれ | |
| 江須扇 2003-10-6 3:43:08
[返信] [編集] EXCHANGEさん、返信ありがとうございます。 > * 訂正です * > > 我々のような「オジサンSE」ばかりになっていくでしょう。 > >end > 「我々のような」−−>「私のような」 に訂正します。 何方からかクレームが有ったのですか? 私も「オジサンSE」なのでこの件にはうなずいてしまったのですが・・・・(笑) タイトルの「我が亡き後に洪水来たれ」はルイ14世か15世が言った言葉と言われており、 要は今の事しか考えていなくて、「あとさきはどうにでもなれ」という考え方です。 こんな考え方の経営者が増え、イエスマンの管理者が右にならえをしていると思います。 一番こまるのは現場の担当者で訳もわからず責任を押し付けれれているというのが現状ではと思っております。 大げさに言えば昨今の工場等のタンク火災もこれに通じるのではと思います。 * 一方、私は「ユーザ」の立場で自社開発をしてきた経験もあるので>「ユーザ」の気持ちもある程度理解できます。 > 導入後わずかな変更を依頼しても「高額な見積もり」を出され、この程度は自分で出来るのに、と思っても「そんなことをされては当社としては保証できない」と脅かされ、他のディーラに替わりたいと思っても「ソース」を出してもらえないので一から開発でかえって高く付く。。といったことはオフコン業界によくあります。 > この不況下で、「新しい機械に買い換えたい」のはやまやまだけど、「もう少しの間」このまま使い続けるしかない。。ハードの価格が高額で、買い換えても「システム」の内容の大幅更新まで予算が取れない、どうせ同じことしかできないのなら、動くうちはこのまま使い続けても同じでは。。 私も解りますが、しかしながら 合理化してコストダウンと手抜きでコストダウンや 次世代のメンバー引き継がなくてコストダウン また、不法コピーしてでのコストダウンは まったく別物と思います。 コンピュータだけではなく工場等の保守の完璧さが日本の伝統でしたが伝統芸能といっしょで伝統を引き継ぐ後継者がいなくなったのでしょうか? >* 業務ソフトウエア(システム)についても「システム構築という別のサービス、商品」なので、 > ユーザには可能な限り自由な「選択肢」があったほうがいいと思います。 「系列」のディーラだけでなく、「自社開発」、「独立したソフトハウス」へ依頼するなど考えられると思います。 これもおっしゃる通りと思います。 ユーザー(利用者)の判断で保守に入る入らないは勝手と思います。 しかし、全てが大人の世界の自己責任で、 壊れた時、つかえなくなったときどう対処するか、 経営者、管理者は正確に担当者に事前説明をして その時に担当者が困らなく責任もとらなくなっていれば問題はありません。しかし往々にして担当者に業務の支障をきたした責任をとらされてしまします。 オフコンはお任せ定食なのでこの部分もとりあえずはハードの維持保守に入るのが前提ですと担当者が管理者、経営者に説明でき、少しでも責任回避を計っており担当者にとってはメリットがあると思います。 | |
| (ごめんなさい。訂正です) | |
| EXCHANGE 2003-10-3 3:24:32
[返信] [編集] * 訂正です * > 我々のような「オジサンSE」ばかりになっていくでしょう。 >end 「我々のような」−−>「私のような」 に訂正します。 | |
| (さらにオジサンはくどくどと。。) | |
| EXCHANGE 2003-10-3 3:05:02
[返信] [編集] * 「ハードの保守」「ソフトの保守」に対価を支払うのは当然だと私は思います。 * 逆に、「ソフトを請け負った会社は」ユーザに対して、かなり長期間にわたって維持するための「技術」「スキル」を保持し続ける義務があると思います。 * さらに、メーカも、ユーザが「対価(契約料)」を払えば、OS、開発ツール、運用ツール、パッチ情報などの技術情報が手にはいるように、積極的に公開を進めていって欲しいと思っています。 * 「リプレースのために、その場限りの技術情報を求める人たち」は論外ですが、 メーカが継続的な契約システムをつくることにより、 A−VXでのシステム構築にさいして、ディーラ、ソフトハウス、ユーザがそれぞれ積極的に参加し、競争できる環境が広がることを私は願っています。 * ああ〜〜、疲れた。。 | |
| 「製品」と「ハード保守」と「ソフト保守」は別なのでは? | |
| EXCHANGE 2003-10-3 1:53:26
[返信] [編集] *「維持保守契約が大前提」というのは私も同感です。また、サービスは有償でなければ維持できないということがユーザに十分理解されていないのも事実です。 * 一方、私は「ユーザ」の立場で自社開発をしてきた経験もあるので「ユーザ」の気持ちもある程度理解できます。 導入後わずかな変更を依頼しても「高額な見積もり」を出され、この程度は自分で出来るのに、と思っても「そんなことをされては当社としては保証できない」と脅かされ、他のディーラに替わりたいと思っても「ソース」を出してもらえないので一から開発でかえって高く付く。。といったことはオフコン業界によくあります。 この不況下で、「新しい機械に買い換えたい」のはやまやまだけど、「もう少しの間」このまま使い続けるしかない。。ハードの価格が高額で、買い換えても「システム」の内容の大幅更新まで予算が取れない、どうせ同じことしかできないのなら、動くうちはこのまま使い続けても同じでは。。 * そこで、パソコン系のシステムへ変わりたいというふうになるのでしょう。 もっともそこには別の問題がいっぱいあるのですけどね。 * ところで、オフコンというかコンピュータ全般のことですけど、 ハード製品、OS製品といった「製品」と、「ハードウエアの保守」と「業務ソフト(業務システム)の保守」はそれぞれ別物と考えたほうがよいのではないでしょうか? * オフコンの特徴は同一メーカによる「製品(ハード、OS、開発ツール)」の一貫性にその本質があるのであり、これはすでに「製品価格」に反映しているはずです。 * 一方ハードウエアの保守は基本的にメーカによって供給されるものだとしても、それは「ハード保守サービスという別商品」なのでユーザによって「定期契約」「随時契約(スポット修理)」といった自由な選択肢があってしかるべきだと思います。(現に実施されていると思いますし、供給者も「メーカ直」以外に「自営保守」というタイプもあります) * 業務ソフトウエア(システム)についても「システム構築という別のサービス、商品」なので、 ユーザには可能な限り自由な「選択肢」があったほうがいいと思います。 「系列」のディーラだけでなく、「自社開発」、「独立したソフトハウス」へ依頼するなど考えられると思います。 * ところが、現在の制度では「製品の販売」と、「技術情報の提供」がすべて「系列ルート」を通じてしか行われないので、 ユーザは、すべて「系列ディーラ」にいわれるままの「高額」な(と、選択肢がないので感じてしまう)サービスに従わざるを得ないのが実情です。日本のメーカのオフコンは特にこれがひどい。 * この点では、日本のメーカはもう少しIBMを見習うべきだと思います。 例えばiサーバ(AS/400)などは、IBMのホームページに、OS400のマニュアルと設定情報が公開されていますし、IBMとサポート契約を結べば、メーカ直で技術情報が入手できます。 * F社のHPのオフコン情報をみてごらん。代理店を通じて登録したユーザしか閲覧できない「鍵マーク」だらけ。 ユーザ向け「情報誌」だって「代理店名」とその「担当者名」を書かなきゃHPから申し込み出来ないでしょう。 * 要するに「オフコン」は、少し製品が高くても「ハード、OS、開発ツールが同一メーカによって提供され、かつ長期にわたって一貫性と継続性が維持される」という点に価値があるのであって、 「系列販売」は必ずしも本質的ではないと思うのです。 * 現状の「ガチガチの囲い込み」が続く限り、SOHO、ユーザ企業内の若いソフト技術者は次第に「オフコン」のまわりに近寄らなくなり、我々のような「オジサンSE」ばかりになっていくでしょう。 * やっぱり「オジサンSE」だね。 ちょっと、話がクドくなってきたかな?? ==追伸== う〜〜ん。こういうことは「オープン系」OSでないと、やっぱり無理なのかなあ。。 「オフコン」に情報の公開を求めるのは、「木によりて魚を求む」のたぐいかなあ。。 だんだん自信がなくなってきました。 | |
| NECオフコンは維持保守契約が大前提です。 | |
| 江須扇 2003-10-2 13:47:40
[返信] [編集] 他社の事はわかりませんがNECオフコン、 システム100、システム3100、システム7200、Express5800/700、600 の場合は業務(オフィス)で使用する(コンピュータ)ということが大前提です。 従ってパソコンショップなどで販売はしておらず、基本的には 販売店(特約店、代理店、ディーラ)を通して販売されており通常は契約書を交わすので販売店と利用者(ユーザー)は特定されます。 さらに業務で使用するコンピュータという事でハードウェア障害が発生し業務に支障をきたさないように維持保守契約を結ぶ事になってます。 維持保守は販売店で行う自営保守とNECの保守専門会社(後述)に委託する委託保守があります。又は、何らかの理由で販売店が携わらない時はNECの保守専門会社の直接保守があります。 つまり業務で使用しているかぎり販売店か保守会社と連絡が取れているのが前提です。 もちろんビジネスなのでお金が必要なのは当然です。 オフコンはその前提の上で使用するという話になっております。 業務で使用するつまり企業収益を得る補助設備でありその設備を維持保守する事は管理者、経営者の義務であり維持するコストが収益に見合わない場合は廃棄すべきです。 この事が良い意味でも悪い意味でもオフコンのオフコンたるところでパソコンとは大きく違うところです。私はそう思っております。 販売店が倒産したとか何らかの理由で販売店とも保守会社とも連絡がとれてない場合は下記のNECの保守専門会社に連絡をし早急に《保守契約》をしましょう。 NECフィールディング http://www.fielding.co.jp/ なお、今まで保守契約をしてない場合はオーバーホールという維持保守できる状態に現状の確認保守作業をしますと言われる場合があります。 その場合は費用が発生します今まで保守料を払って無い場合その総額以上になるかもしれません。 また、経過年数多くて維持保守が出来ないといわれる場合もあります。 その場合は保守会社にA?VXを熟知しており現状のシステムを移行できる信頼できる販売店を紹介してもらいましょう。 | |
| 鉄道と道路(自動車) | |
| 江須扇 2003-10-2 3:43:42
[返信] [編集] このサイトでいきなり鉄ちゃんネタ? いえ違います。 地上を走る交通手段として鉄道と道路(自動車)がありますが一番違う所は 鉄道上で走る列車は全て企業が運営しているというです。 道路上を走る車は営業車、自家用車が何の区別もなく混沌と走っています。 何が言いたいかと申しますと私はA−VX大好き人間ですが自宅にはオフコンを所有しておりません。 なぜかと言えばオフィスコンピュータだからです。 高いからいえいえ、販売中止になりましたが610のスタンドアロンであれば大昔のパソコン等に近くそれなりの値段です。 しかし、私は自宅でオフコンを使って企業収益をあげる業務は行っておりません。 オフコンはオフコンです。企業が使って企業収益をあげる為の補助手段です。鉄道会社が自社の車両を管理保守しているのは、それで企業収益を得てるからです。 オフコンで企業収益をあげている手段として使っているなら、つまり設備であるなら、設備の維持、保守は経営者、管理者の義務です。 つまり、維持、保守する事が収益を生まないということでしたら早く捨てるべきです。 それにしてもメーカーであるNECも販売代理店も保守会社も表現方法は違うかもしれませんが、ユーザー(利用者、お客様)にその事を地道に根気よく伝え理解していただく努力をしてないのではと思います。 古いマシンを使用するのは自由を思いますが結果的に業務に使うのに壊れてからどうしようと騒いでいるのは キツイいいかたですが業務システムを甘く見ているからとしか思えませんがどうでしょうか? 個人でも使うパソコンと同列で考えて欲しくないというのが私の考え方です。 また、これもメーカーに言えることですが、「ただ、無い」と言うのではなく有償ソフトウェアは有償である事はユーザーによく理解していただく必要があると思います。 | |
| (意見広告): プロの会社は顧客の「過去資産」に責任をもて!! | |
| EXCHANGE 2003-10-1 14:11:28
[返信] [編集] * このHPで何回か「質問」というのが掲載され、私も親切心で数回にわたって「回答」もしくは「ヒント」のようなものを入れさせて頂きました。メールでのやりとりをさせて頂いたこともあります。 * このやりとりで気づいたのですが、 お一人の方は、現在は純粋にユーザ(職場での運用責任者)の立場で運用上お困りの案件でしたので、最後まで気持ちよくやりとりが出来ましたが、 そのほかの方については、よくよくお聞きすると、 その問題になっているシステムは、 実は、”「私たちが作った」システムですが ” ”現在わかるものがいない ” ので このHPで ”お教え頂きたい ” ”助けてほしい ” と、いうものでした。 * たしかに、そのシステムは同じ会社ではあっても「昔の先輩たち」が作ったもので、「自分たちは」分からないのに突然その担当に配属されて「困っている」。。 というのはお気の毒なことと、心からご同情申し上げます。 そして、このような「場」で他人の気持ちを害することをあまり言いたくはありません。 *** しかし ****** あえて、私は言いたい、 「もし、あなたのおっしゃっている内容がほんとうのことなら、 それは、実はあなたの会社の問題です。 システム構築をひきうける「プロ」の会社としての貴社内部の問題です。」 たとえ昔に引き受けたシステムであれ、ひとたび「ソフト会社」としてある「お客様」をお引き受けしてシステム構築したのであり、そして今もその方があなたの会社のお客様としてとどまっておられるのであれば、 たとえ年数が経ち、担当者が替わっていても「資料」や「仕様書」を引き継ぎ、「出来る者」もしくは「出来るスキル」を保持し続けるのが当然の責任ではないでしょうか? こういうことは、「普段から」しておくべきことで、窮してからこのようなところへ「助けを乞う」というのはプロとして「恥ずかしい」ことと思いませんか?(会社の恥をさらしているようなものです) * そして内容はふつうA−VXをやっていればごく「基本的な」な内容ばかり。 私には信じられないのです。例えば、5年やそこら前に、そこそこ大きなマシンで開発しておきながら、「A−VXのデータをエクセルや、CSV形式に落とす方法を使ったことがない、またはやり方を全く知らない」などということが。。 A−VXでシステム作りした会社ならそんなことは「常識」ではないでしょうか? そしてまた信じられない。 「納入当時、顧客に納めたテープメディアに何が入っているか分からない。読み出す方法も全く知らない。仕様書も残っていない。」などということが。。。 ひねくれて、性格の悪い私は、「本当は、A−VXのリプレースをねらっている連中が、偽って質問をしているのでは?」 とすら想像したくなってしまいます。 * いずれにせよ、「A−VX」から「自分たちの都合の良いシステム」に乗せ替えたいだけのために、「その場限りの助け」を求めている連中に、私は一生懸命、力を貸そうとしていたのだろうか? と思うと悲しくなってきました。 * 私は、決してA−VXに盲目的に惚れ込んでいるわけではありません。必要な場合はVBや、JAVAで純粋なオープン系システムを組みます。 そしてA−VXが、まだまだ多くの不十分な面を持っていることも事実です。 * しかし、このHPはターラヤンさんが始めた、「A−VXに関心のある者同士の交流の場」であると思いますので、 「A−VXをおとしめるための方法を伝授する」のではなく、「A−VXを有効利用するための建設的な方法を教え合い」、 「A−VXをより高めていくようNECに対して発言していくような場」にしていきたいと思います。 == 追伸 == ごく直近に、ターラヤンさんがフーさんに返答されていた内容を拝見させて頂いて、とても感銘を受けました。 そこには、質問者と既存のシステムに対する思いやりがあふれていたように思います。 > 一番良いのは、オフコンを購入した販売店/ディーラーに相談してみることだと思います。 システムを構築したところが、一番良く知っているはずです。 >end | |
| 30年前のセールストーク | |
| 江須扇 2003-10-1 13:47:01
[返信] [編集] >そのため、OSはWindowsに、データはOracleにして、誰でも扱えるようにしたい、という思いです。) この言葉で、あくまでもイメージですが30年前のセールストークを思い出しました。 ------------------------------------------------------------------------------- 専用のコンピュータルームは必要ありません、一般の事務所内に設置できます。 専用の運用要員もいりません。誰でも扱う事ができます。 専用のプログラマも必要ありません、COBOLライクの会話形式のBESTで誰でもプログラムが作れます。 と1973年華々しくNECオフィスコンピュータは登場しました。 「母さん、誰でも扱えるオフコンは何処行ってしまったのでしょうか?(Mama do you remenber?)」 「人間の証明」風に叫んでしまいましたが、いつからオフコンは難しくて敷居の高いコンピュータになったのでしょうか? 何度も言いますが私はOracleの方が敷居が高いです。 | |
| (600は「買い」だ!): その1 「まだ迷っている方へ」 | |
| EXCHANGE 2003-10-1 6:26:09
[返信] [編集] * 「以前から古いオフコンを使っているが、そろそろ新しいものに買い換える必要があるな?」 「コンピュータには何かというと高い金をかけてきたが、 何とかならんのか、この不景気に。。」 「近頃はパソコンが安いと聞いたし、パソコン系のサーバで一からやり直した方が今後のことを考えるといいのかしら?」 「でも、以前からのソフトに従業員たちも慣れているし。。」 「PCLANで売り込みに来たセールスが、オフコンは将来なくなる、それにオフコンではパソコンにつながらない、だれでも使えない、 といっていたな?。そういえばうちのオフコン、データをパソコンに取り込んでいないようだ。。」 「でも、PCLANのセールス、見積もりを見ればなんだかんだと訳の分からない項目が並んでいてトータルすれば結構な値段じゃないか! パソコンは安いって言ってたのに。。」 * いろいろ、お悩みの経営者、管理者の方もおられると思います。 * まずお断りしておきますが、私は、NECの回し者(メーカサイドの人間)ではありません。 (メーカサイドの方、うさんくさい呼び方してごめんなさい!!) ユーザの立場から始めて、途中からシステム構築、ソフト制作を「生業」とするようになった立場から、少しばかりお話をさせて頂きたいと思います。あくまでも参考としてお聞きください。 * 「あらゆるケースに当てはまる」などというアドバイスはあり得ないので、それぞれの会社の状況、システムの必要度、担当者のレベル等々、個別の条件を考えて行けばそれぞれに違った回答が出てくるとは思います。 あくまでも一般的な「参考意見」です。 * 一応、状況を限定します。 =設置状況= (1)NECの旧タイプの、いわゆる「オフコン」(S7200以前)のマシンを現在も使い続けている。 (2)端末台数で1〜30台程度。 (3)いわゆる「中小企業」で、現在のマシンは「メイン」のコンピュータである。 =現在の問題点= (1)マシンが古くなって時々問題が起こる。販売店より「保守契約が出来にくい」などといって、買い換えの要請がある。 (2)業務で発生したデータをパソコンで分析するなどといった情報有効利用があまり出来ていない。 (3)今後のことを考えて、次にどのような形のシステムを導入すべきか迷っている。(このまま「オフコンで乗せ換えか?」「パソコン系システムの方がよいのか?」等) =個人的背景= * 私は、分野から言うと、一番好きなのがサン(SOLARIS)、その次がLinux、その次がMS(Windows)、その次がホスト系(AS、AVXの順)です。 * しかし、業務系のシステム構築では評価の順序は、がぜん変わります。 一番がホスト系(AVX、ASの順。順序注意!!) 次がサン(SOLARIS+oracle) それ以下はドングリの背比べ。。(つまりあまり信用していないということ)です。 * それでは以下、OS比べなどという「オリンピック」はやめにして、「迷える経営者」にとって重要な問題に焦点をあてて考えていきましょう。 (続く) | |
| (もうちょっとだけオマケ):「リコー文化について」 | |
| EXCHANGE 2003-9-29 1:13:58
[返信] [編集] * リコーがMX500シリーズというUNIXベースのオフコンを発売したころ、「これからはUNIXの時代です!!」と書かれたパンフレットをもらいました。 * そこにはこれらの時代はUNIXがビジネス用途で主流になる時代がきた云々。。 そして最後の方には、リコーが「UNIX日本総代理店」になったと書かれていました。 * これは、ジョークですが、もしあのUNIX路線を「根気よく」続けていれば、今やLinuxの時代、 リコーは今頃主流となり、 「日本総代理店」の権利を行使して、 日本のSCOになれていたかも。。。。 | |
| ユーザの立場から見た:「リコー文化」について | |
| EXCHANGE 2003-9-29 0:10:06
[返信] [編集] * 「リコーのオフコン」に関して、江須扇さんの興味深いお話をお聞かせ頂いてうれしく思っています。私はコンピュータ関連のコースの出身ではなく、また業界に勤めたりした経験もなく、基本的にユーザとしての立場でしか接することが出来ませんでしたので、江須扇さんのお話の中で、供給する側の方々の「楽屋裏」をかいま見た感じがして、「なるほど、あの時そうだったのか。。」と今になって納得させられた気がします。 * そこで、「ユーザの側」からみたリコーのオフコン、リコーの文化についてすこし話をさせていただこうかと思います。 * リコーの場合、自社製品も含めて様々なメーカとOSを手がけたため一見して「脈絡のない」感じがしますが、実はそこには共通した「文化」のようなものがありました。 * それは、 (1)RAPSと呼ばれる「標準化」の文化 (2)「販売管理標準システム」と呼ばれる一連のパッケージソフト (3)「ペンタッチ入力」に始まるMMI(マン・マシンインターフェイス) (4)RAPID −−> RSPF とつながる独自開発言語 です。 このうち(3)だけが独自なハードに関わっており、他はすべてソフト製品(知的資産)です。 いわゆるコンピュータメーカとしての確固たるものがなかったリコーは、むしろこうしたものでもって勝負しようとしたようです。 * COMPOS以前の「ペンコール」というマシンの頃に(1)〜(3)の原型が作られ、COMPOSの時代(リコム2000)になって確固たるものになりました。(4)についてはCOMPOSになって出現したのですが、ペンコールの後半の時期には「REAL−1」(RICOH easy adaptable LANGUAGE)というものがありましたからこれがその前身と言えば前身でしょうか。。 * いずれにせよこれらはリコーオフコンの独自文化として、機種が変わりOSが変わっても少しずつ修正を加えて移植されるのが常でした。 これらは「仮想独自マシン」「仮想ケースツール」としてリコーの製品の独自性と統一性、そして開発の効率化を担い続けたと思われます。 * ユーザからみてこれらはNEC、IBMといった「メーカ」にない「ユニーク」で「小回りの利く」すばらしいものでした。 またリコーは常に時代を鋭く先読みするのがうまく、リコーが始めたことは少し後になると世の中の主流になる、といったことがよくありました。 * ただ、リコーの弱点は、すばらしい「発想」で時代に先駆けて手がけるのは良いのですが、肝心の「ものになる」までにやめてしまい、もう少し根気よく続けていれば時代の主流になれたのに。。というものばかりでした。 * 「業務パッケージ」にしてもオービックのようにはなれませんでしたし、 「RSPF」にしてもLANSAというところまで行きませんでしたし、「UNIXのビジネスマシンでの展開(MX500)」も、LINUXの時代まで持ちこたえることが出来ませんでしたし、「MYツールとPC事業」だって消えていきました。。(MYツールは、時代に先駆けて(?)フリーウエアになってしまいました) 最近は「LOTUSノーツ」に凝っておられるようですね。 * 「販売のリコー」といわれるように、時代に先駆けて「売れるもの」にシフトしていく、 というのもユーザにとって「いい面」もあり「困った」面もあります。 リコーの尻馬に乗って「S36、OS2」+「ペンタッチ」を使ってシステム構築したあのパン製造会社、今頃はどうしてるかなあ?? 高価なRSPFを導入したあのIBM代理店、今頃はどうしてるかなあ?? ちなみに私はリコーのこのような性質が途中からわかってきましたので、熱心な売り込みにもかかわらず「RSPF」は買いませんでした(よかった!)。 だってそのときのセールストークでは、「IBMだけでなく、NECのCOBOLも一部のパターンが生成できる。今後すべてのプログラムパターンが生成できるようになる」とおっしゃていたにもかかわらず。。 * 私が、ダサイ(失礼!)NECに鞍替えしたのは、その「根気の良さ」を評価してのことです。 * でも、今でもリコーのオフコン(特にCOMPOS系)は「すばらしい」とおもっており、ちなみに我が社ではRAPIDで組んだシステムで、現在も「リコムI(アイ)」が保守契約もなしで3台も実稼働しています。今や我が社は「世界最大のリコムユーザ」となりました!! | |
| リコーのオフコン(続きです) | |
| 江須扇 2003-9-28 13:11:31
[返信] [編集] 前回からだいぶたってしまいましたが、続きを書きます。 MX500シリーズの前に最後のRICOMであるIシリーズの事を書く事を忘れてました。 このシリーズはMXシリーズと併売され、その後のIBMとのOEMのRicoh−iシリーズが出てからも併売されました。 名前が紛らわしいのでゴチャゴチャに話がなってしまいますが、RICOM−Iはそれ以前のCOMPOSが動く最後のシリーズということです。 このころはパソコン台頭し始めており、スタンドアロンオフコンは冬の時代に入ってしまったと言うか無くなるのではという時代でした。 リコーはマイツールという独自仕様のカルクソフト(リコーではワープロ機能、データベース機能もあるので、一つのソフトで出来るので融合ソフトと称していました。)のみを動かすソフトウェアもハードウェアも一体のパソコンを販売していました。 このマイツールのハードウェアは日立のOEMで、日立のB16シリーズと互換性がありました。 (後にIBMと提携した時はIBMのOEMのPS/55系もありました。) ソフトウェアはソードのPIPSに似ていました。この辺の詳しい事情は忘れました。 本題に戻すと、オフコンデータのパソコンの有効利用という話が盛んになり、N5200のLANシリーズも評判になっていた時期でした。そこでLANシリーズに対抗してマイプラン、マイファイル、マイフィギア(マイグラフは他社で商標登録済みで使えなかったそうです)をリリースしました。 その後、このRICOM−Iシリーズも偶々か、意識しては解りませんがCPUがインテル互換でしたので、リブート方式でMS−DOSを動かすことができるようになりました。 (当初のRICOM2000はザイログ社のZ80と聞いていました) そこで、マイツールも動かす事ができました。 今にして思えば、N5200にやり方に似ていました。PTOSという独自OSとMSDOSがやはり動きましたね。 その後、リコーとNECの仲は大人の関係(ビジネス上取引をするが仲が悪いという事です。)でむしろリコーはIBM側に属すイメージとなりました。 余談ですが日立とはパソコンとワープロのOEMの関係でそれ以上はなかったようです。 (俗に日立は製造部門と販売部門が分かれていて、販売部門の口出しは無く、営業が提携するという話がなかったようです。) 個人的にはCOMPOSは非常に安定したOSだったのでハードウェアの製造を諦めた時、COMPOSをN5200に乗せるか、日立のB16に乗せるか、その後のPS/55シリーズに乗せるかして生き延びて欲しかったと思います。 が死んだ子の年を数えてもしかたがないですね。 リコーは全く別の方法でRicoh−iシリーズを出しました。 IBMは所謂ベイパーウェア(VAPORWARE)でAS/400を直ぐにでも出すような事を言っていましたが、なかなか販売しませんでした。 従って提携当初は、PS/55のOS/2仕様をi735、System36をi736として販売していました。 スタントアロンの場合はCOBOL/2(NECとは無関係です)という名前でMicroFocus社のLebel?COBOLのIBMのOEM版というところでしょうか。リコーのCOMPOSの互換機能はサブルーチンで提供されました。 COMPOS−>UNIX(MXシリーズ)−>OS/2となったので、レベルアップではなくレベルダウンでした。 イーサネットではなく専用のネットワーク(トークンリング?)OS/2同士を繋いだクラスタ接続をLANマネジャーで繋ぐ事もできたのですが、COBOL/2のREAD LOCK が ステータスが帰ってくるだけで、自分でループしないと次に進んでしまい、排他機能の制御ができませんでした。 OS/2は最初のバージョンJ1.0で非常に不安定で苦労した記憶があります。 此れを業務で使ったのはリコーだけはなかったのでしょうか? 私から見ればリコーはIBMの体の良いOS/2のバグだし担当でした。 その後のJ1.1 PMプレゼンテーションマネージャもあまり良くなく、不安定になる位なら、J1.0を使い続けるという感覚でした。当時はPMのWindows切替より、J1.0の全画面切替の方が安定していた記憶です。 i736(S/36)はSSPのOS下でRPGでネイティブの画面一括入出力方式で開発する方法と SIF接続ですが、NECでいうRDB/FILEアクセスキットの方式で、i735のCOBOL/2で開発しDBだけをi736を使うという項目単位入出力方式もとれました。 この部分は今から15年位前に出来ていたというのはIBMの技術力はすばらしかったと思います。 当時もNECもAVX/NETを使ったかどうかは忘れましたが、分散方式はとれたと思います。 しかし、集中方式でもNECの場合は項目単位入力方式なので特に必要がなかったと思います。 (汎用機のACOSとN5200では有効な手段だったようです。) その後、AS/400が発売され、下位機をi740というシリーズ名で販売されました。 下位機と言ってもS/38クラスなので、多くは売れなかったと思います。1年位してから、本格的にS/36クラスの更に下のクラスが発売され、ようやく本格的に売る事ができたのですが、本来全てをOS/400での開発にできれば良かったのですが、売り方を間違えたので、市場にはCOMPOS、UNIX、OS/2、SSP、OS/400、A−VXと6種類のOS下で開発されたシステムあり。それをサポートしながら、増員はしたというもののいままで、COMPOSとA−VXだけしか知らない要員で元号対応、消費税対応、システム移植作業をしていた為現場は大混乱でした。 今となっては結果的にはUNIXとOS/2とSSPはつなぎであったので、COMPOSを引っ張るだけ引っ張って、A?VXで逃げていれば良かったと思います。PS/55にCOMPOSを乗せOS/400との分散方式も開発して本格的に安定してからOS/400のシステムを開発していれば混乱もすくなかったと思います。IBMとしてはNEC製品を売られる事が困るので巧く話をしたのでしょう。 まんまとIBMの戦略に乗っかった為、その後の運命はどうなったのでしょうか? |
| 新規投稿 | スレッド表示 | ツリー表示 | 投稿順表示 | i-mode | トップ |
BluesBB ©Sting_Band